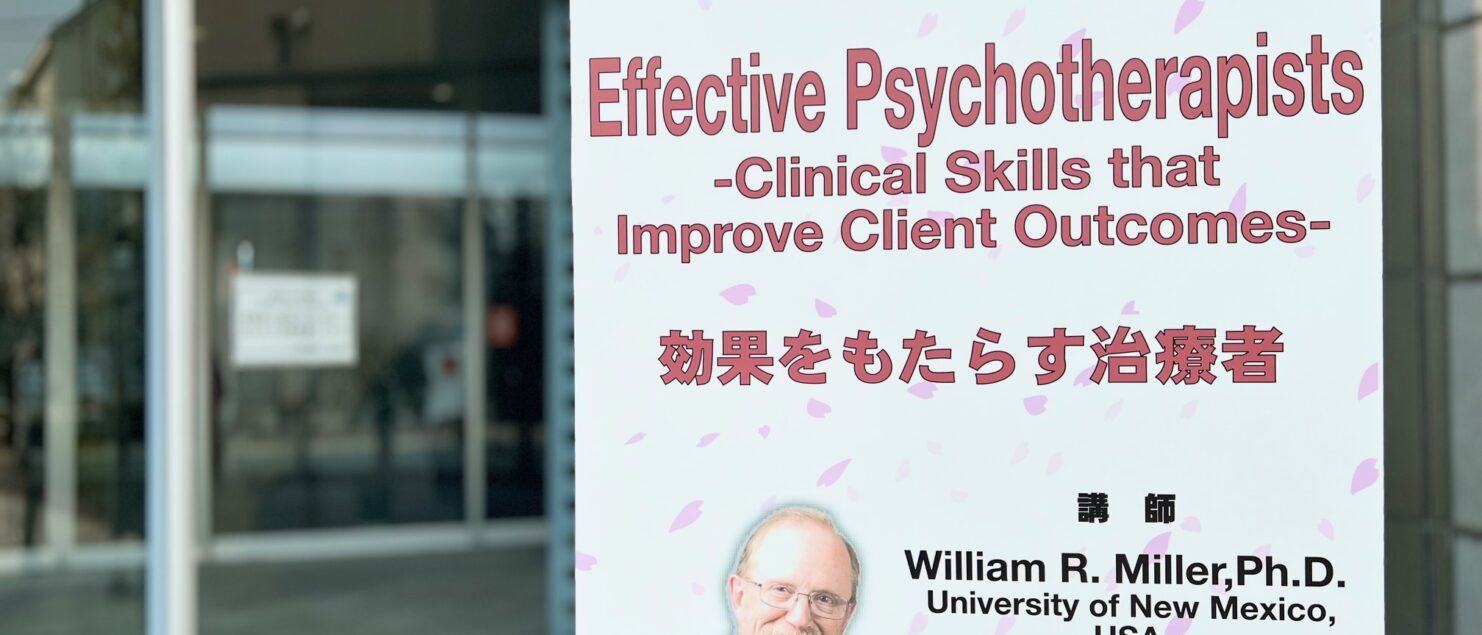【驚きの事実】どの技法を使うかより、「誰が支援するか」の方が重要説!
先日、William R. Miller 博士(ニューメキシコ大学名誉教授)の特別講演会に参加しました。
言わずと知れた「動機づけ面接法(MI)」の創始者。
私自身、長年MIの考え方に支えられてきた支援者のひとりです。来日の報せを聞き、迷わず申込みました。
このブログでは、講演で得た気づきと、支援をおこなう上であらためて大切にしたいことを、自分の整理も兼ねて記録してみたいと思います。

※アウェー感はありつつもMiller博士の近くでの写真撮影に成功した私
技法よりも「誰が」支援するか
講演の序盤で紹介されたのは、アルコール依存症に対する三つの心理療法(CBT、12ステップ、MI)による介入効果の比較研究。
170名を対象とした大規模な調査で、いずれの技法を使っても治療効果が証明され、その根拠となる断酒継続の日数には差が見られなかった、との結果が共有されました。
ということは、どの技法を使っても効果は変わらないということなのか? では、実際に治療効果を左右するものって何なのか?
そんな疑問が自然と浮かび上がってきました。
もう一つ、興味深い研究が紹介されました。
9人のカウンセラーが同一の行動療法マニュアルを使い、共通のトレーニングとスーパービジョンを受けたうえで、アルコール使用障害のクライエントに対応するという研究。
このセッションの様子は、3人のスーパーバイザーが観察し、カウンセラーごとの「正確な共感性」に関するスコアを付けたとのこと。
結果は、同じマニュアル、同じトレーニングを受けているにもかかわらず、担当するカウンセラーによって治療効果に明確な差が出てしまったのです・・・
とくに、共感性の低いカウンセラーのもとで治療を受けたクライエントは、セッションを受けずに自宅学習していた人よりも悪い結果になっていたというのです。
一方で、共感性の高いカウンセラーによる治療は、より良い治療効果を示しており、この「共感性」の違いが、結果に大きく影響を及ぼしていたことが分かりました。
つまり、どの心理療法を使って治療するかよりも、共感性の高いカウンセラーが治療を担当することの方が、心理療法を提供する上では重要ということになります。

「共感性」は、技法よりも強力な治療因子
こうした研究が突きつけてくることは、「支援者の共感性の高さ」こそが治療効果を左右する重要な要素だ! という現実です。
支援の現場では、「支援を標準化しよう」「統一された対応をしよう」という言葉がよく聞かれます。もちろん、クライエントの混乱を避ける意味ではとても大事です。
でも、同じ対応をしているはずなのに、Aさんが関わると落ち着き、Bさんが関わると混乱する。そんな現象に、心当たりはないでしょうか。
日頃の支援で感じていたその正体は、「共感性の度合い」の違いで説明がつくかもしれません。
「関係性が大事」って、よく聞く。でもその中身は?
福祉や心理の現場では、繰り返しこう言われます。
「支援は、関係性が9割」だと。
でも、こう問われるとドキッとします。
「その関係性って、具体的には何ですか?」
Miller博士の講演で、その答えが明確に示されたような気がします。
それは、70年にわたる心理療法研究のレビューから、「効果をもたらす治療者」に共通する8つのスキルが紹介されたからです。
詳しくは、書籍で熟読してもらうと良いかと思いますが、以下に、簡単に私なりの解釈でご紹介したいと思います。
SKILL① 正確な共感
これは単なる優しさや同情ではなく、クライエントの内的世界を丁寧に、誤りなく、そして理性的に、思いやる姿勢のことです。
この共感が欠けると、治療効果は著しく低下し、ときに「何もしない方がマシだった」という結果すら招くことがあります。
人は誰しも「自分のことをちゃんと分かってほしい」と強く願っています。
その願いが満たされない限り、次のステップへ進むことは難しいのだと、あらためて感じました。
SKILL② 肯定的配慮
クライエントの強みや成果、変化に向かう意欲や努力などに光をあてて、それに対する敬意や称賛を積極的に伝えること。
このちょっとしたフィードバックが、治療への抵抗を和らげ、支援者との関係性を深めていく鍵となります。
MIでは是認という言葉で表現されていますが、これは単なる褒めるといった「上から目線の称賛」ではなく、クライエント自身の経験や価値を具体的に言葉にして伝えるところがポイントです。
褒められることに対して「自分を操ろうとしている」という疑念を覚える人もいますが、それでも強みや長所を認識して、大切に取り扱う姿勢は大事です。
SKILL③ 純粋性/誠実さ
支援者が自分の内面に気づきながら、飾らず、正直にクライエントと向き合うということ。
私たちはつい「できる支援者」でいようとします。けれど、その背伸びが、かえってクライエントに「届かない存在」という印象を与えかねません。
「不誠実さには、自分を隠すことが含まれる」とありました。逆に、誠実さとは、自分の内面と言動が一致している状態と言えるかもしれません。
支援者には、適切な量やタイミングでの自己開示が求められるので難しさを感じます。一方で、一般的に自己開示をする人は、好感が持て、信頼できる人、という認識をもたれることが多い、ということも知っておく必要があります。
SKILL④ 受容
どんな背景を持っていても、まず「知らない、だから知りたい」の姿勢を持つこと。
情報が多く入りすぎる時代だからこそ、先入観や偏見、レッテル貼りや批判的な気持ちを持たずに「ビギナーズ・マインド」で相手と向き合う、という言葉が心に残りました。
「誰かに受け容れられたと感じることで行動を変えることができる」
どこかで聞いたことがあるフレーズだと思っていたのですが、DBTの創始者 Marsha M. Linehan(マーシャリネハン)も同じことを言っていました。
SKILL⑤ 焦点化/フォーカス
「どこに向かっているのか知らなければ、別の場所に行き着くハメになる」という言葉を聞いて、ハッとしました。
たしかに、相手側の都合で立てられた『正解プラン』の押し付けほど、意欲を奪われるものはありません。クライエントと目標を共有し、達成するための一貫した計画をもつことが大切です。
だから、「どこに行きたいのか」を尋ね、「そこに行くには何が必要か」を一緒に考える、といった共同の意思決定のプロセスをたどること。
方向性が明確でさえあれば、危機に直面したとき、遠回りをするかもしれないけれど、向かうべきポイントに向かうことはできます。
SKILL⑥ 希望/期待
クライエントが希望を持てないときは、支援者の希望を貸してあげることが大切です。そして、支援者の楽観的な態度も大切です。
どんな支援を提供しても成功と失敗があるはずです。でも、このように二極化した考え方よりも、「三歩進んで、二歩下がる。そうやって成長するもの」という前提があれば、希望を持ち続けることができます。
知識が増えるほど、効果だけでなくリスクにも目が向き、慎重になりすぎる自分がいます。でも思えば、無知だった頃の方が、危うさはあっても自分を信じて支援していた気がします。
だから今こそ希望を忘れず、一歩を踏み出す勇気を示したい、自信をもって「この支援は有効だ!」と伝えていきたい、そう気づかされました。
SKILL⑦ 喚起/引き出す
「人は、自分の口から出た言葉をもっとも信じる」
ですから、引き出すものはクライエントの欠点ではなく「強み」が対象です。これはMIの大前提でもあり、「チェンジトーク」を引き出す理由でもあります。
クライエントがすでに持っている「変わりたい気持ち」をどれだけ引き出せるか、そして、クライエントが語る変化の言葉にどれだけ耳を澄ませているか。
その積み重ねが、支援の持続性と効果を支えていきます。
※チェンジトーク:変化に向かう言葉(変化への動機、希望、行動、必要性、理由、決意)
SKILL⑧ 情報提供/助言
「伝える」ではなく「届ける」
情報提供とは、支援者の意見を押し付けて抵抗を煽ることではなく、動機を引き出し、選択肢を示し、自己決定を支えることだと定義し直す必要があります。
どんなに正しい情報も、クライエントの関心や好奇心がなければ、心には届きません。

まとめ
福祉の現場では、多くの場合、利用者の皆さんが支援者を選ぶことはできません。
むしろ、誰が担当するかは支援者側の都合によって決められているのが現実です。
だからこそ、私たちはこの前提を直視する必要があります。
「選ばれる立場にないからこそ、選ばれるに値する支援者でありたい」
この想いが、支援の質を高める原動力になるのだと思います。
「共感性の高さ」といった目には見えにくい要素が、確実に支援の効果に影響している。
だから私たち支援者は、Miller博士によって紹介された「効果をもたらす治療者」に共通する8つのスキルを、日々磨いていく姿勢が求められるのだと感じました。
一緒に、選ばれる支援者を目指して成長していきましょう。

国家資格:公認心理師・精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士
その他:SE™プラクティショナー(トラウマ療法)/USPTベーシックレベル/ TSM(トラウマセンシティブマインドフルネス)修了 /MBSR(マインドフルネスストレス低減法)講師養成トレーニング受講中